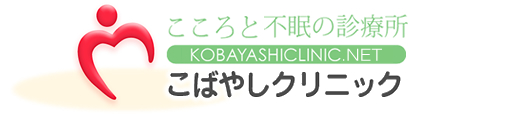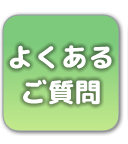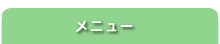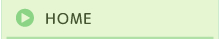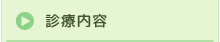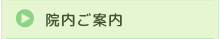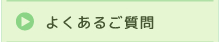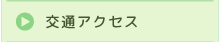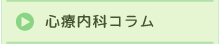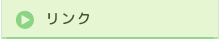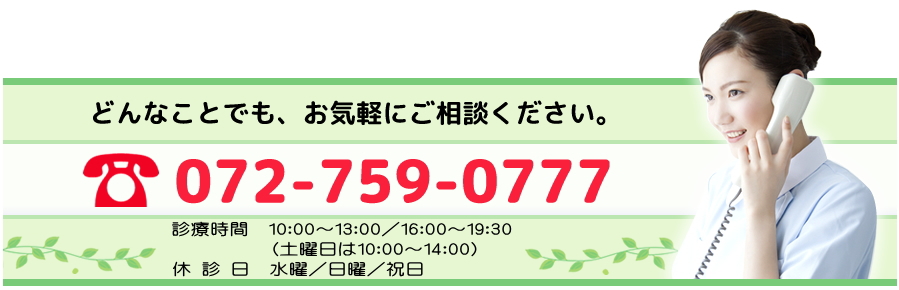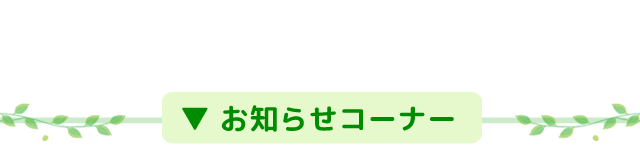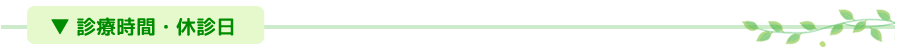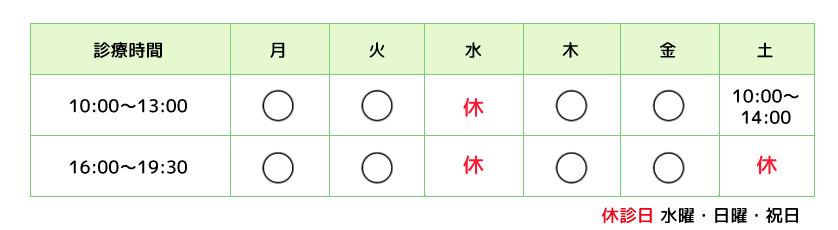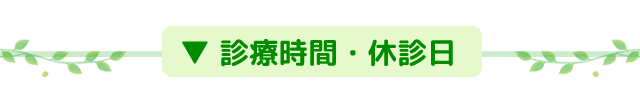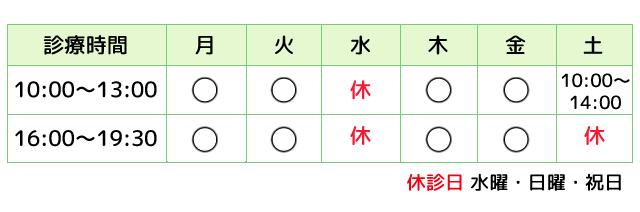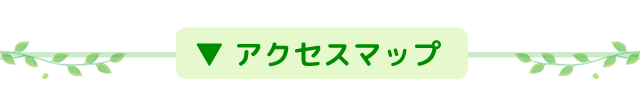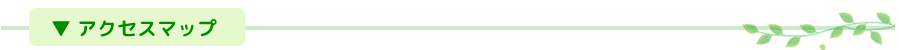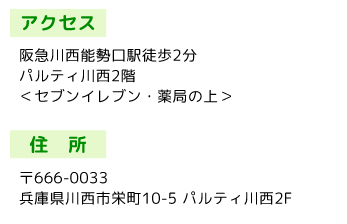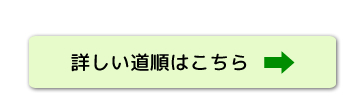日内変動と言えば、まずは体温、そして血圧や心拍数が挙げられるのでしょうが、人は誰でも朝と夜の体温も違えば血圧も変化しますので、1日を通してある程度の変化であれば病気を疑うことはないはずです。
日内変動と言えば、まずは体温、そして血圧や心拍数が挙げられるのでしょうが、人は誰でも朝と夜の体温も違えば血圧も変化しますので、1日を通してある程度の変化であれば病気を疑うことはないはずです。
ところが、あまりに体温が上がったり、心拍数が急激に早くなれば、何かの病気を疑って病院で検査を受けることでしょう。
ただ、日内変動が起こった時にうつ病のような精神疾患などの病気を疑うことは少ないかもしれません。
ところが激しい日内変動で内科などを受診しても、身体の異常は認められないこともあり、精神疾患の病気を懸念して心療内科や精神科の受診をすすめられることも少なくないようです。
たとえば、心の病気の中でもうつ病の患者さんには日内変動が顕著に現れることがあり、朝はすんなり目覚めたにもかかわらず、出かける時間になると気力が衰え外出できないといった患者さんもいます。
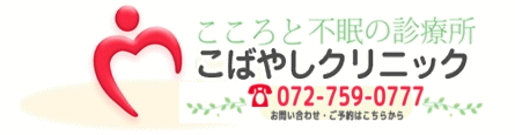
ところが、日内変動に気付かずに、疲れているだけとか睡眠時間が足りていないだけといった自己判断で見逃してしまい、さらに激しくなることもないとは言えません。
この日内変動を病気として自覚できるかどうかは、やはり心療内科や精神科を受診してきちんとした診断を受け、適切な治療を受ける必要があると考えます。
あまりに日内変動が激しくて周囲とのコミュニケーションがうまくいかないといった事例もありますが、目で見て病気とわかるようなものではないので、周囲の理解を得ることが難しいために休職したり仕事をやめたりといったケースもあるようですが、適切な病気治療を受けて職場復帰をされる方も多いので、手をこまねいているのであれば、まずはこばやしクリニックにご相談いただければと思います。
当クリニックはさまざまな心の病気に対応し、地域に根差した医療を目指した心療内科であり、神経科・精神科のクリニックでもありますので、敷居の高さを感じることなく気軽にご来院いただけると思います
日内変動の原因は?
「日内変動」という言葉が病気を指す場合、精神的または生理的な症状の一部として、24時間周期で起こる症状の変動を指していることが考えられます。この場合、「日内変動」とは、日中の時間帯や夜間に症状の強さが変化する現象を指します。以下にその原因を挙げます。
うつ病(特に気分障害)
うつ病の患者では、症状が日内で変動することがよくあります。朝は特に症状が強く、夕方や夜には少し楽になることがあります。この現象は、脳内の神経伝達物質(例えばセロトニンやドパミン)の変動や、体内時計(サーカディアンリズム)の影響に関連しています。
躁うつ病(双極性障害)
躁うつ病でも、日内変動が見られることがあります。特に躁状態では、日中にエネルギーが高まり、夜になると急激に気分が沈むことがあります。逆にうつ状態では、朝に最も気分が落ち込み、夜に少し回復することがある場合があります。
自律神経失調症
自律神経のバランスが崩れることで、日内での症状の変動が見られることがあります。例えば、朝起きたときにめまいや頭痛が強く、午後には落ち着くことがあります。自律神経が正常に働かないことで、体温調整や心拍数、血圧が不安定になることが原因です。
不安障害
不安障害の症状も、日中に変動することがあります。特に朝は不安感が強く、午後や夜になると少し楽になることがあるのは、体のホルモンや神経伝達物質が時間帯によって異なるためです。
睡眠障害(例:不眠症)
睡眠不足が日内変動を引き起こすことがあります。十分な睡眠が取れないと、日中に強い疲労感や集中力の低下を感じ、夜になってもその影響を感じることがあります。慢性的な睡眠障害は、気分や身体的な症状の変動を引き起こす可能性があります。
ホルモンの変動
ホルモンバランスの変化も日内変動の原因となることがあります。例えば、女性の月経周期や妊娠、更年期においてホルモンが大きく変動するため、日内で体調が変わることがあります。
薬の副作用
一部の薬(抗うつ薬や抗精神病薬など)は、服用後の時間帯によって副作用が強く現れることがあります。薬の効果が時間とともに変動することが、症状の変動に影響を与えることがあります。
体内時計(サーカディアンリズム)の影響
体内時計は、体温やホルモン分泌、気分に影響を与えるため、日内変動の原因となります。特に、朝と夜で異なる体内のメカニズムが働くことが、気分や体調に変化をもたらすことがあります。
日内変動が顕著な病気に関しては、個々の症状や体調によって異なりますので、症状が続く場合や気になる場合は、専門的な医師の診断を受けることが重要です。
日内変動を改善する方法
病気による日内変動を改善する方法は、症状の種類や原因に応じて異なります。以下にいくつかの一般的なアプローチを挙げますが、どの方法も医師の指導の下で行うことが大切です。
1. 生活習慣の改善
規則正しい生活リズムの確立
体内時計(サーカディアンリズム)を整えることは、日内変動を改善するために非常に重要です。毎日同じ時間に起床し、寝る時間も一定にすることで、体調や気分の安定を図ります。
十分な睡眠
睡眠の質を向上させることは、日内の気分や体調の安定に寄与します。睡眠環境を整え、寝る前のスマホやパソコンの使用を控えるなど、睡眠の質を高める工夫が有効です。
食事の管理
バランスの取れた食事を摂取し、血糖値の急激な変動を避けることが、日内変動の改善に役立つことがあります。特に、朝食をしっかりと摂ることが、体調の安定に寄与する場合があります。
2. ストレス管理とリラクゼーション
瞑想や深呼吸
瞑想や深呼吸などのリラクゼーション技法は、自律神経のバランスを整えるのに役立ちます。特に、日中にストレスを感じたときにリラックスすることで、症状が緩和することがあります。
運動
定期的な軽い運動(ウォーキングやヨガなど)は、精神的な安定を促進し、日内変動の症状を改善する効果があります。運動はエンドルフィンを分泌し、気分を安定させる効果があります。
3. 薬物療法
抗うつ薬や抗不安薬
うつ病や不安障害に伴う日内変動に対しては、抗うつ薬や抗不安薬が効果的な場合があります。これらの薬は、神経伝達物質のバランスを整え、気分や症状の安定を図ります。
ホルモン療法: ホルモンバランスの乱れが日内変動を引き起こしている場合、ホルモン療法が有効です。例えば、更年期障害や月経不順に対してホルモン補充療法が行われることがあります。
睡眠薬や安定薬
睡眠障害が原因の場合、医師の指導のもとで適切な睡眠薬や安定薬を使用することがあります。
4. 認知行動療法(CBT)
認知行動療法は、うつ病や不安障害、ストレスに関連する症状を改善するために効果的な心理療法です。日内変動を引き起こす考え方のパターンを変えることができ、症状のコントロールに役立ちます。
CBTは、感情の変動や不安を管理するための具体的な方法を学ぶことができ、日々の生活で活用することができます。
5. サーカディアンリズムの調整
光療法
日内変動が生体リズムによるものである場合、光療法が有効なことがあります。朝、自然光を浴びることや、特定の時間に人工光を浴びることで、体内時計を調整することができます。特に季節性のうつ病(SAD)などでは効果が見られることがあります。
メラトニンの補充
睡眠と覚醒のサイクルを調整するために、メラトニンを補充する方法があります。これは、夜間に体内で分泌されるホルモンで、睡眠のリズムを整える働きがあります。医師の指導のもとでの使用が推奨されます。
6. 薬の調整
一部の薬は、副作用として日内変動を引き起こすことがあります。薬の服用によって症状が悪化する場合、医師に相談して、薬の変更や調整を行うことが重要です。
7. 社会的サポートの活用
サポートグループやカウンセリング: 同じ病気や症状を持つ人々とつながり、サポートを受けることも日内変動の改善に役立ちます。自分の状態を理解し、他者との交流を通じて安心感を得ることができます。
8. 専門医による評価と治療
日内変動が続く場合や症状が重篤な場合は、専門的な医師の診断と治療が必要です。心理的、身体的な原因を明確にし、個別の治療法を提案してもらうことが大切です。
結論
日内変動の改善には、生活習慣の見直しや薬物療法、心理的アプローチを組み合わせた治療が有効です。症状の原因に応じて適切な対策を取ることが重要であり、専門的な医師のアドバイスを受けながら治療を進めることが最も効果的です。