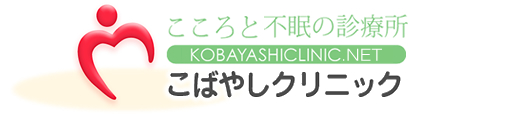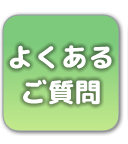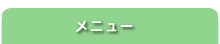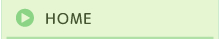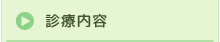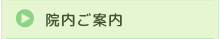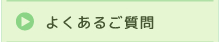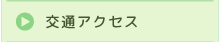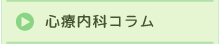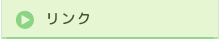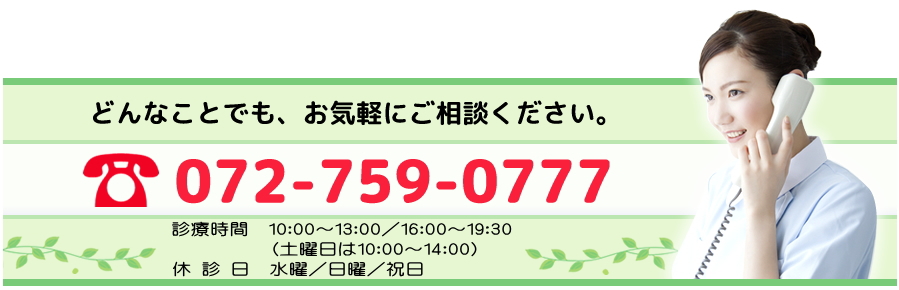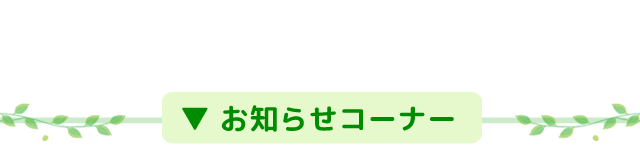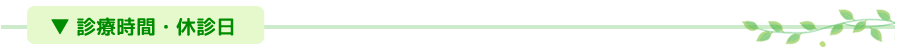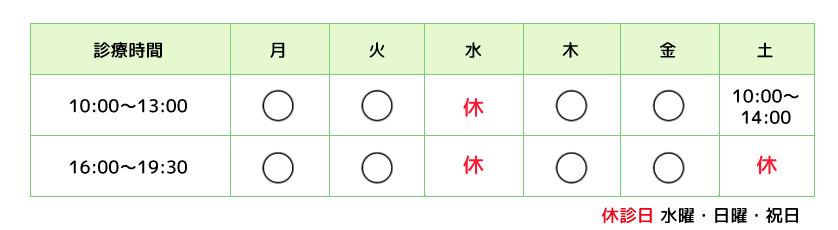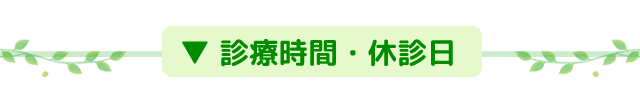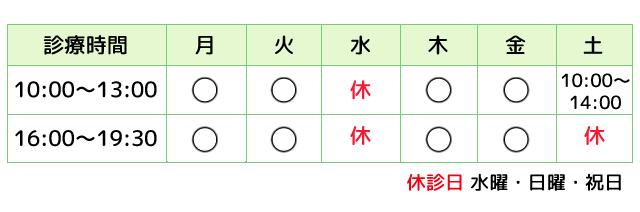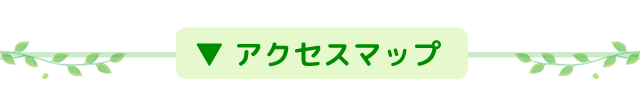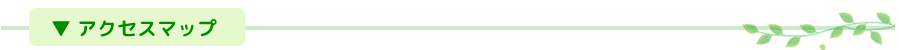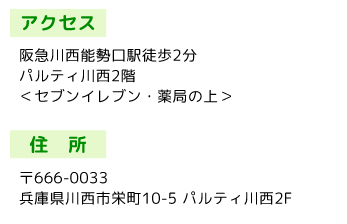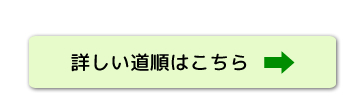いつまでたっても躁鬱病が治らないと焦ることもあるでしょうが、やはり焦りは禁物です。もちろん、躁鬱病に限らず、病気や怪我が治らないために仕事を休めば収入にも影響して不安が尽きないことでしょう。また、このまま一生治らないのではと、絶望的になることもあるかもしれません。
いつまでたっても躁鬱病が治らないと焦ることもあるでしょうが、やはり焦りは禁物です。もちろん、躁鬱病に限らず、病気や怪我が治らないために仕事を休めば収入にも影響して不安が尽きないことでしょう。また、このまま一生治らないのではと、絶望的になることもあるかもしれません。
しかも、それが躁鬱病のような精神疾患であれば、ご家族の精神的な負担も大きいはずです。たとえば、お子さんが躁鬱病で不登校になり、就職も望めずにいれば、親がいなくなった将来のことが気がかりなことでしょう。ただ、一人で悩まずに、一度心療内科を受診していただければ、光が見えてくるかもしれません。
当クリニックには、躁鬱病が治らないために心療内科を転々と受診した後に来院される患者さんもいます。中には、心療内科でアドバイスさえ受ければすぐにでも改善すると思われている方もいるようですが、躁鬱病治療はわずか数回の診療で済むものではなく、早期に治らないと判断してしまうのはあまりおすすめできることではありません。
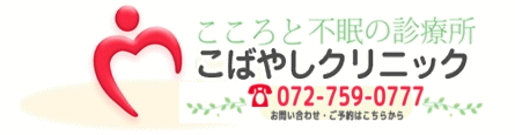
当クリニックでは、患者さんが安心して治療を継続できるように、そして患者さんの緊張感を取り除いて受診していただけるように環境を整え、信頼していただけるようにコミュニケーションをとりながら疾患と向き合って行きますので、治らないといった思い込みは一旦忘れていただいて、通院していただければと思います。
また、躁鬱病だと気付かないまま、躁鬱病の症状に悩まされている方も多いのではないでしょうか。どんな工夫をしても不眠症が治らない、いつまで経っても食欲不振が治らないと悩んでいませんか。
さらに、浪費癖が治らないとか、すぐに感情的になる癖が治らないと思っている場合も、もしかしたら躁鬱病の兆候かもしれません。
もし、兵庫や大阪で躁鬱病やさまざまな精神疾患のために心療内科を受診するのであれば、川西市のこばやしクリニックにご相談下さい。当クリニックは、一般的な心療内科や精神科の重苦しいイメージとは違い、明るく穏やかな雰囲気を大切にしたクリニックになります。
躁うつ病の改善の兆し
1. 気分・感情の安定
・気分の上下が以前より緩やかになってきた。
・ハイテンションや落ち込みの波が短く・軽くなってきた。
・「ちょっと落ち込んでも、時間が経てば回復する」と感じられる。
2. 睡眠・生活リズムの回復
・夜に眠れるようになり、朝スムーズに起きられる。
・睡眠時間が安定し、昼夜逆転が減ってきた。
・食欲や体調が安定してきた。
3. 思考・行動の落ち着き
・考え方が極端にならず、冷静に判断できる時間が増えた。
・計画を立てて行動できるようになってきた。
・無理な活動(過剰な予定や買い物など)が減った。
4. 人間関係・社会生活の回復
・家族や友人との会話が自然にできるようになってきた。
・学業・仕事・趣味に少しずつ取り組めるようになった。
・「またやってみようかな」という気持ちが湧いてきた。
5. 自分で症状に気づける
・「今ちょっとハイになってるかも」「落ち込んでるな」と自覚できる。
・気分の波が来ても「対処すれば大丈夫」と思える。
・主治医やカウンセラーに正直に状態を伝えられる。
改善の兆しは「大きな変化」ではなく、
「少し楽になった」「少し安定した」という小さな積み重ねで表れることが多いです。
改善を安定させるための生活習慣
1. 睡眠・生活リズムを整える
・毎日同じ時間に寝起きする(休日も大きく崩さない)
・夜更かし・徹夜を避ける(睡眠不足は躁転のきっかけになりやすい)
・眠れない時は「無理に寝よう」とせず、リラックスできる行動をとる
2. 食生活の安定
・朝食をしっかり食べて体内時計を整える
・栄養バランスのとれた食事(炭水化物・たんぱく質・野菜を意識)
・カフェイン・アルコール・エナジードリンクを控える
3. 適度な運動
・軽いウォーキングやストレッチを無理なく続ける
・強すぎる運動(極端な筋トレやマラソンなど)は躁状態を誘発することもあるので注意
・「心地よく疲れる」程度がベスト
4. ストレス管理
・スケジュールを詰め込みすぎない
・学業・仕事・人間関係で無理を感じたら、早めに休む・相談する
・趣味やリラックス法(読書、音楽、深呼吸、瞑想など)を生活に取り入れる
5. 薬・治療の継続
・症状が落ち着いても自己判断で薬をやめない
・医師と相談しながら治療を続ける
・気分や体調の変化を日記やアプリで記録して、主治医と共有する
6. 人とのつながりを保つ
・家族や友人に「調子が良い時・悪い時のサイン」を共有しておく
・孤立せず、安心して話せる相手やカウンセラーを持つ
・SNSでの比較や深夜の長時間利用は控える
7. 自分の波に気づく習慣
・「気分が高ぶってきたな」「少し落ち込みが長いな」と早めに自覚する
・気分チェック表やアプリを活用する
・小さな変化でも主治医に報告する
ポイント
・規則正しい生活と無理しすぎない工夫が最も重要。
・「元気すぎる」「落ち込みすぎる」両方のサインに早めに気づくことが安定につながります。