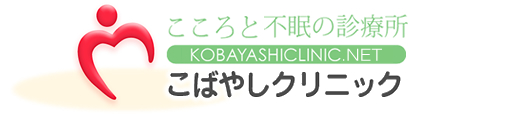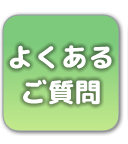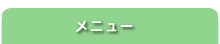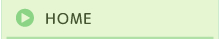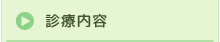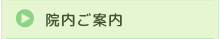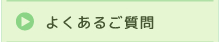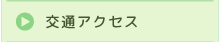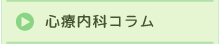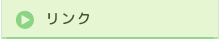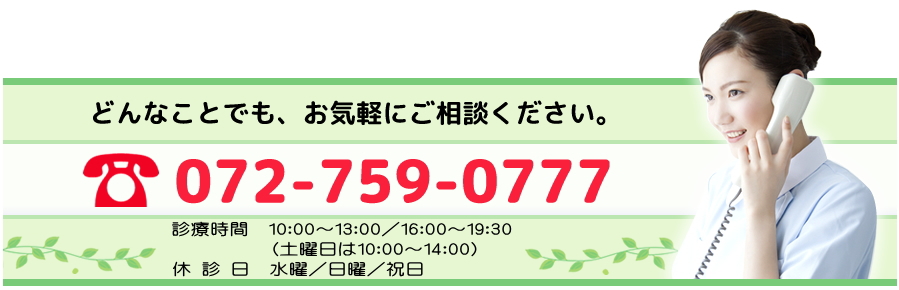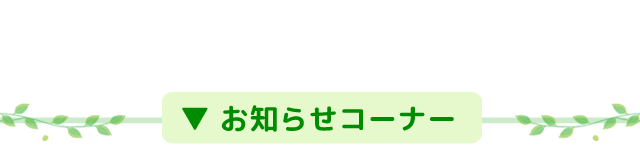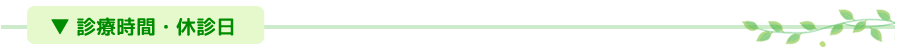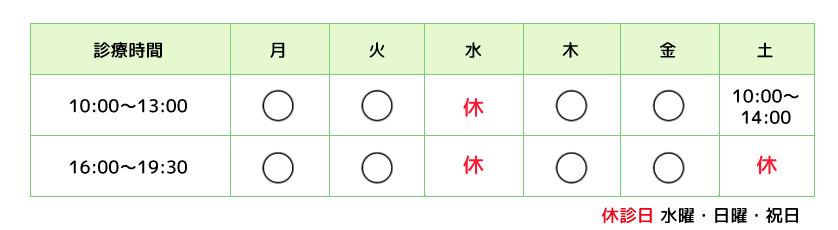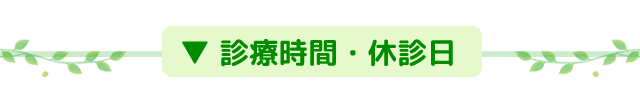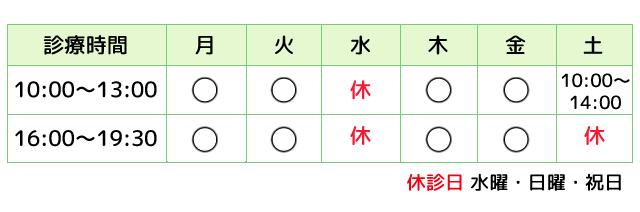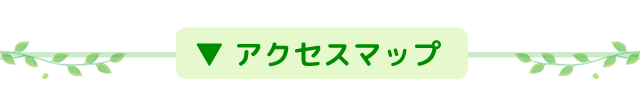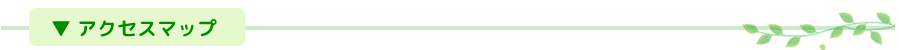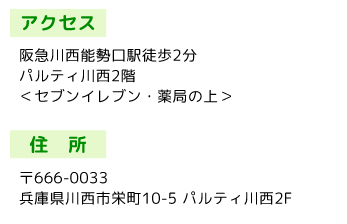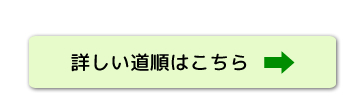躁鬱病かどうかの診断、そして治療を開始するにあたっては、判断基準となるガイドラインがあります。そのガイドラインは、医療に携わる側のガイドラインということになりますが、患者さん側にもどのようにして躁鬱病と向き合うかといったガイドラインもあるでしょう。
躁鬱病かどうかの診断、そして治療を開始するにあたっては、判断基準となるガイドラインがあります。そのガイドラインは、医療に携わる側のガイドラインということになりますが、患者さん側にもどのようにして躁鬱病と向き合うかといったガイドラインもあるでしょう。
ガイドラインとは指針・指標という意味になりますが、医療の現場ではガイドラインが重要な役目を持ち、最新・最善の治療法などが示されていますが、特に躁鬱病のような精神的な疾患の場合はガイドラインが重要だと言えるでしょう。
もちろん、どんな病気にしてもガイドラインが判断の基準になるわけですが、躁鬱病はレントゲンやCT、血液検査の数値などで判断できる病ではなく、さらに身体的な痛みや苦しみが現われないこともあり、ガイドラインがあることで適切な診断ができることになります。
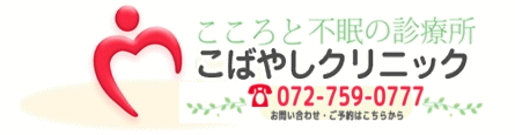
たとえば20回以上受診を繰り返して、ようやく躁鬱病と診断されることもないとは言えません。そこで、必要になるのが患者さん側の躁鬱病に関するガイドラインです。
ガイドラインには躁鬱病だと気付くこと、ご自身の病状を理解すること、そして躁鬱病との付き合い方などが示されています。
心の病はご自身では気付かないことも多く、受診するまで数年間もかかってしまったという方もいるはずです。気持ちの浮き沈みが激しい、人との接し方が日によって極端に変わるなど、思い当たることがあれば早めに受診していただきたいと思います。
また、躁鬱病の症状には眠れないとか食欲がない、注意力が散漫になり疲れやすいといった症状が伴うこともありますが、なかなかそういった症状が躁鬱病とは結び付かずに、受け入れられない患者さんもいます。
また、急に元気になってやる気が出てくると周りも安心してしまい、病気を忘れがちになりますが、慎重に病と付き合わなければ症状が繰り返してさらに重症化することもありますので、きちんと受診して治療を続けていただきたいと思います。
躁鬱病のガイドライン
ガイドライン内容:主要ポイント
以下は、上記ガイドラインを参照して導かれる、双極性障害に関する「標準的な考え方・治療方針」です。
1. 診断・評価
・DSM/ICDなどの公式診断基準を用いて、躁・軽躁・うつ・混合型の各エピソードを区別する。
・発症時期、持続期間、重症度、前歴(何回起きているか)、躁転リスク、家族歴、併存疾患(不安障害、ADHD、物質使用など)を評価する。
・自殺リスクや自傷行為の有無、他の危険因子(身体疾患、薬剤併用など)を確認する。
・身体検査・血液検査(肝機能、腎機能、甲状腺機能、電解質など)を基礎として行う。
2. 急性期治療(躁状態・軽躁・混合型)
・躁状態が明らかであれば、迅速な対応が重要。
・第一選択として、気分安定薬(リチウム、バルプロ酸など)を使う場合が多い。
・非定型抗精神病薬(第二世代抗精神病薬:クエチアピン、アリピプラゾールなど)を使うことも広く認められている。
・重症例・精神病症状を伴う例では、併用療法(気分安定薬 + 抗精神病薬など)を用いることが多い。
・薬剤反応を見ながら、用量調整・変更を行う。
・入院を必要とするケースでは、治療体制を強化する。
3. 急性期治療(抑うつ状態)
・抗うつ薬を用いる際には慎重を期する必要があり、単独使用は原則避け、気分安定薬または抗精神病薬と併用することが多い(躁転リスクを考慮)という指針が多い。
・抗うつ薬の中でも、三環系抗うつ薬の単独使用はガイドライン上、慎重または推奨されないとされることが多い。
・非定型抗精神病薬(例:クエチアピンなど)は、抑うつ相にも効果を示すものがあり、単独あるいは併用で使用されることもある。
・治療抵抗性例では、修正型電気けいれん療法(m-ECT)も検討され得る。
4. 維持期治療・再発予防
・双極性障害は再発率が高いため、まずは 薬物治療を継続 することが前提とされる。
・維持期には、躁およびうつエピソードの双方を予防できる薬剤(リチウムなど)が重視される。
・抗精神病薬を維持期に用いることも一般的である。
・抗うつ薬を維持期に用いる場合は、躁転リスクを考慮して慎重に行うべき。
・定期的なモニタリングと、再発の早期兆候(気分変動、睡眠リズムの乱れなど)への対応計画をすでに立てておく。
・減薬・中止を試みる場合には段階的に行い、再発徴候を注意深くモニタリングする。
5. 心理社会的介入・補助的治療
ガイドラインでは、薬物療法に加えて、以下のような心理社会的治療を併用することが強く推奨されます
・心理教育(psychoeducation)
患者本人・家族に疾患の性質、再発兆候、治療の意義・副作用などを理解してもらう
・認知行動療法(CBT)
抑うつ思考パターンの改善、ストレス対処スキルの習得
・対人関係‐社会リズム療法(IPSRT:Interpersonal and Social Rhythm Therapy)
日常リズム(睡眠・活動・食事など)の安定化を図る
・家族療法・家族支援
家族とのコミュニケーション改善、支援体制づくり
・その他補助法
ストレスマネジメント、リラクゼーション法、セルフモニタリング、ライフスタイル調整など
これらを併用することで、再発予防・治療継続性・生活機能の改善が期待されます。
6. モニタリング・副作用管理・特殊事情
・薬剤使用中は、定期的に血液検査、肝機能・腎機能・甲状腺機能・代謝系(血糖・脂質)などをチェックする必要がある。
・リチウム、バルプロ酸、あるいは併用抗精神病薬では特有の副作用リスク(腎機能・甲状腺機能・体重増加・代謝症候群など)に注意。
・妊娠・授乳中、老年期、児童・思春期例では特別な配慮が必要。ガイドラインでもこれらの特殊群への注意が述べられている。
・併存疾患(例:心疾患、糖尿病、てんかんなど)がある場合、それとの相互作用・影響を考慮した薬剤選択・用量調整が求められる。
・服薬遵守(アドヒアランス)を高めるためのサポート(心理社会的介入、フォローアップ体制など)が重要。
・患者の価値観・希望を反映する「共同意思決定(shared decision making)」の姿勢が重視される。
7. エビデンスの強さ・限界・
各ガイドラインは、エビデンスの強さ・推奨度を明記しており、すべての治療選択に対して確固たる高水準のエビデンスがあるわけではない。
・臨床試験で対象となる患者は典型例であることが多いため、実臨床の複雑な例(併存疾患・薬物抵抗例など)への当てはめには注意が必要。
・新薬や併用戦略、特殊群へのエビデンスは現在も発展途上であり、ガイドライン更新や臨床研究の進展により見直される部分がある。
・抗うつ薬使用・躁転防止戦略など、一部分野で専門家意見が入りやすい領域がある。