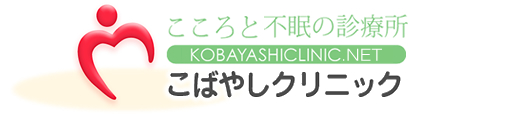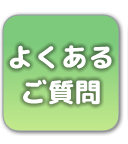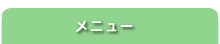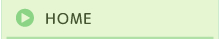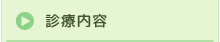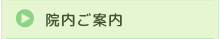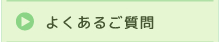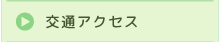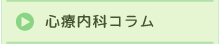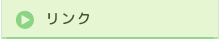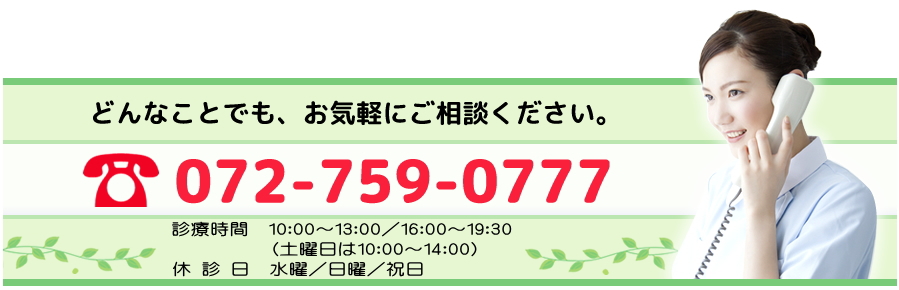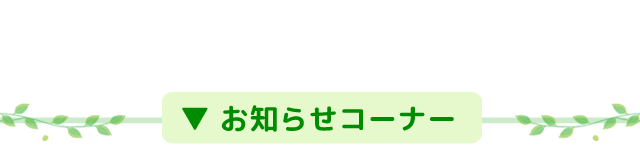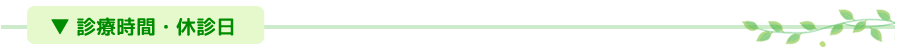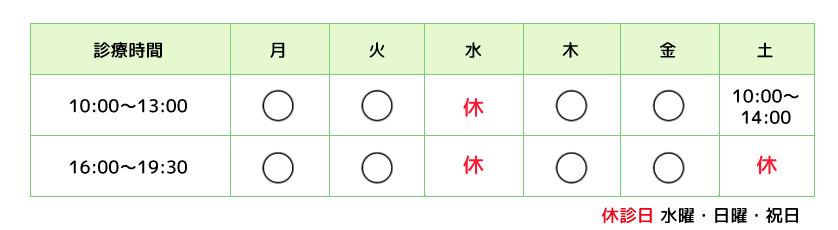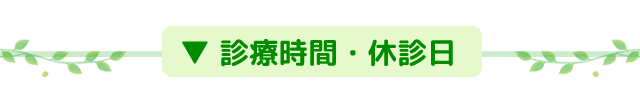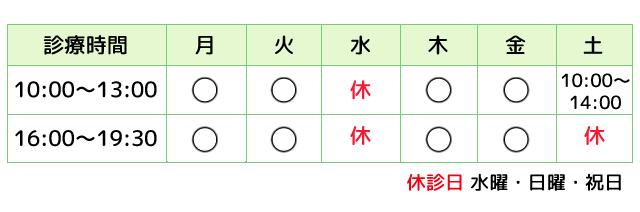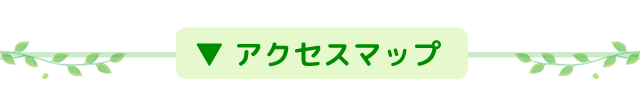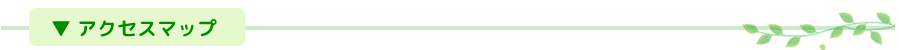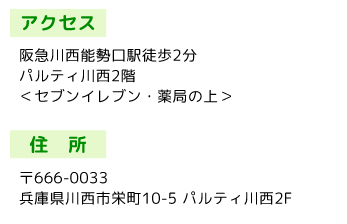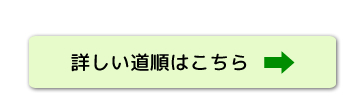なんとかして躁鬱病を治したいと思った時、カウンセリングさえ受ければすぐにでも改善すると思っている方もいるようです。中には、電話相談のような形でカウンセリングを数回受ければ、躁鬱の状態から嘘のように脱出できると思う方もいるでしょう。
なんとかして躁鬱病を治したいと思った時、カウンセリングさえ受ければすぐにでも改善すると思っている方もいるようです。中には、電話相談のような形でカウンセリングを数回受ければ、躁鬱の状態から嘘のように脱出できると思う方もいるでしょう。
もし簡単なカウンセリングだけで躁鬱が治ったと感じるようであれば、おそらくそれは躁鬱ではなく、環境の変化や心理状態に影響するような出来事に遭遇したことによる気持ちの揺れなのかもしれません。
もちろん、そういったことが引き金となって躁鬱を発症することもないとは言えませんが、心療内科医によるカウンセリングでなくても、親身になって相談できる人がいるだけで、気持ちが落ち着いて躁鬱かと思うような状態から抜け出すことができるのではないでしょうか。
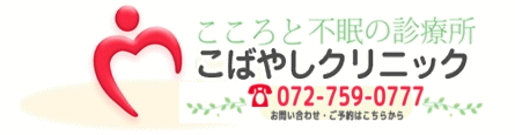
また、まれにE-mailでのカウンセリングや診断を求められる方もいらっしゃいますが、やはり実際に患者さんを目の前にして診断させていただきたいと思いますので、ぜひご来院いただければと思います。
よくある例として、特に躁鬱の場合はご本人が心療内科や精神科の受診を拒んでいるために、ご家族が心配してカウンセリングを受けさせたいというご相談をいただくことがあります。おそらく精神科を受診するとなれば気持ちが余計に落ち込み、憂鬱になることもあるでしょう。
ただ、これまでの多くの心療内科や精神科の病院のイメージとは異なり、明るく穏やかで落ち着きのある当クリニックの雰囲気は、たとえ躁鬱の患者さんであっても安心して受診していただくことができ、治療に専念していただけると思います。
もし、躁鬱を何とかしたいと思われているようであれば、一時的なカウンセリングではなく、落ち着いて時間をかけて治療を続けることが望ましいと思います。
鬱病のカウンセリングはどういった事を行うのか?
躁鬱(双極性障害)のカウンセリングでは、薬物療法と並行して行われることが多く、主な目的は「気分の波を理解し、生活を安定させるためのサポート」をすることです。内容はカウンセラーや状況によって異なりますが、一般的には次のようなことを行います。
① 気分や生活の振り返り
・気分の変動(躁状態・うつ状態)を一緒に整理する
・睡眠・食事・生活リズムの記録(気分日誌など)をつけて確認する
・ストレス要因やトリガーになりやすい出来事を見つける
② 病気や症状への理解(心理教育)
・双極性障害の特徴や経過、再発のサインについて学ぶ
・「自分の躁とうつはどんなパターンか」を把握する
・周囲への伝え方や、理解してもらう工夫を考える
③ 認知行動療法(CBT)
・気分の落ち込みに伴う「ネガティブな考え方」を客観的に見直す
・躁状態での衝動的な行動を振り返り、対処の仕方を練習する
・不安やイライラに対して呼吸法やリラクゼーションを取り入れる
④ 生活習慣の安定化
・睡眠・食事・運動のリズムを整えるアドバイス
・お酒やカフェインなど気分を乱しやすい習慣を見直す
・ストレス管理法(趣味、リラクゼーション、タイムマネジメント)
⑤ 人間関係や社会生活への支援
・家族やパートナーとの関わり方の調整
・職場や学校での困りごとの相談
・必要に応じて家族へのカウンセリング(家族療法)
⑥ 危機対応と再発予防
・再発の兆候(睡眠の乱れ、過活動、気分の落ち込み)を早めに察知
・兆候が出たときの「対処プラン」を一緒に決めておく
・自傷や衝動的行動のリスクに備える安全策